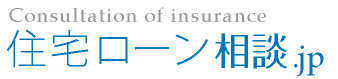| 諸費用の種類 | 支払先 | 支払時期 | |
|---|---|---|---|
| 印紙代 | 税務署(住宅ローン契約書に貼付) | 住宅ローン契約締結時 | ○ |
| 融資事務手数料 | 借入先金融機関 | 資金実行時 | △ |
| フラット35物件検査手数料 | 検査機関 | 検査申請時 | △ |
| 抵当権設定登記費用 | 法務局(登記所) | 登記申請時 | △ |
| 抵当権設定のための司法書士報酬 | 司法書士 | 登記申請依頼時 | ○ |
| 住宅ローン保証料 | 保証会社 | 資金実行時 | △ |
| 団体信用生命保険料 | 生命保険会社 | 資金実行時、毎年 | △ |
| 火災保険料・地震保険料 | 損害保険会社 | 資金実行時、契約期間満了時 | ○ |
ローンの利用で必要な費用は? - よくある質問 - 住宅ローン相談.jp
HOME > よくある質問 > ローンの利用で必要な費用は?
よくある質問
ローンの利用で必要な費用は?
※税金に関する情報は、平成22年度税制を記載しています。
住宅を取得する際には、物件の購入金額以外に税金や手数料、引越し費用などがかかります。
これらは現金での支払いがほとんどですので、頭金とは別に準備しておく必要があります。
諸費用は金融機関や契約内容によっても異なりますが、物件価格の1割が目安と言われています。
売買契約締結時や引渡し時、入居時などそれぞれに費用がかかりますが、ここでは、住宅ローンを利用する際に必要となる費用とそのポイントをご紹介します。
次の表のとおり、必ず支払う費用と支払わなくてもよい場合がある費用がありますので、賢い計画を立てましょう。
ローン手続の際に必要となる費用
※必ず支払う費用:○ 支払わなくてもよい場合がある費用:△
<ポイント1>印紙代(印紙税)
住宅ローンを借りるときには金銭消費貸借契約書を作成しますが、契約書1通毎に所定の収入印紙を貼らなければなりません。
これを印紙税といいます。
契約書に収入印紙を貼り、印鑑などで消印することによって、印紙税を納めたことになります。
税制等については、参考情報としてご利用いただき、詳しくは税務署等にご確認ください。
印紙税の税額
| 借入金額 | 税額 |
|---|---|
| 100万円超500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超1,000万円以下 | 10,000円 |
| 1,000万円超5,000万円以下 | 20,000円 |
| 5,000万円超1億円以下 | 60,000円 |
※住宅や土地を購入時の売買契約書、住宅建設時の工事請負契約書にも必要です。
<ポイント2>融資手数料
融資を受ける金融機関に支払う事務手続の手数料です。
【費用】
金融機関によって異なりますが、平均的な手数料は3万円~5万円程度です。
フラット35の場合、定額(3~5万円程度)または定率(融資額×2.1%等)としている金融機関などがあります。
<ポイント3>フラット35物件検査手数料
フラット35を利用する場合は、建設する住宅が耐久性などの技術基準に適合するかどうか物件検査を受け、適合していることを証明する適合証明書の交付を受ける必要があります。申請先は、住宅金融支援機構と協定を締結している指定確認検査機関または指定住宅性能評価機関です。
【費用】
各機関によって異なりますが、目安として、新築住宅(一戸建て)で2~3万円、中古住宅(一戸建て)で4~6万円程度です。
<ポイント4>抵当権設定登記費用(登録免許税)
住宅ローンを借入れ、抵当権設定を登記する際には、「登録免許税」が必要となります。登記を行う際に、登記印紙で法務局(登記所)に納めることとなります。
【費用】
・床面積が50m2以上であること、中古住宅の場合は、築後25年以内(木造の場合は20年以内)などの要件に該当する場合(平成23年3月31日までの特例措置)
借入額×0.1%
・上記の要件に該当しない場合
借入額×0.4%
【フラット35の登録免許税】
・平成19年3月31日までに申込みを行った場合でも、平成21年4月1日以降に抵当権設定登記申請を行う場合は、課税されます。
・平成19年4月1日以降に申し込む場合は、抵当権設定登記申請の時期にかかわらず課税されます。
財形住宅融資の登録免許税
非課税です。
<ポイント5>抵当権設定のための司法書士報酬
住宅ローンを利用し、住宅又は土地に抵当権を設定する場合に、法務局(登記所)への登記申請を司法書士に依頼するときに支払う報酬です。
【費用】
登記の内容や依頼する司法書士によって異なります。
<ポイント6>住宅ローン保証料
返済不可能となった場合に備え、連帯保証人の代わりに保証会社に保証を依頼するために支払う費用です。
【費用】
借入金額、借入年数、保証会社によって異なります。
民間金融機関の保証料は2,000万円(返済期間30年)借りたときはおおよそ40万円程度。フラット35のようにそもそも保証人が不要なローンもあります。
<ポイント7>団体信用生命保険料
団体信用生命保険に加入すると、万一、返済の途中で加入者が死亡または高度障害状態になった場合に、保険金で住宅ローンの残額が返済されます。
フラット35の場合は、加入が融資の条件ではありませんが、ほとんどの方が加入しています。民間金融機関のローンは、加入が融資の条件となっている場合が大半です。
【費用】
保険料は、借入残高、借入期間によって異なります。あらかじめ金利に上乗せされる場合もあります。
フラット35では、加入した場合は別途負担が必要になります。
<ポイント8>火災保険料・地震保険料
火災保険については多くの金融機関で加入が義務化されています。地震保険については任意加入としている金融機関が多いようです。
掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断転写・転載・公衆送信などを禁じます。
Copyright©
住宅ローン相談.jp All Rights Reserved. / Powered by 京応